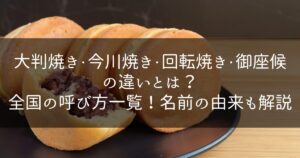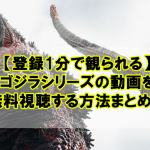「大判焼き」「今川焼き」「回転焼き」「御座候」などと呼ばれるあんこ菓子。
見た目も味もそっくりなのに、なぜか呼び方が違います。
実はこれらは同じ“円形あんこ菓子”で、地域や時代によって名前が変化してきたものなのです。
江戸時代に生まれた「今川焼き」をもとに、明治期には「大判焼き」、関西では「回転焼き」として広まりました。
さらに兵庫の「御座候」や熊本の「蜂楽饅頭」など、地域ブランドに発展したものもあります。
本記事では、それぞれの違いや発祥地、全国での呼び方一覧、そして名前の由来までをわかりやすく解説します。
Contents
大判焼き・今川焼き・回転焼き・御座候の違いまとめ
見た目も形もほとんど同じ「大判焼き」「今川焼き」「回転焼き」「御座候」。
実はどれも基本的には同じ円形のあんこ入り焼き菓子で、違いは「地域の呼び方」と「発祥地」にあります。
生地に小麦粉を使い、金型で両面を焼くスタイルは共通で、味や食感の違いはほとんどありません。
それぞれのルーツをたどると、江戸時代に「今川焼き」が東京・今川橋付近で誕生したのが始まりです。
明治期には大型化した「大判焼き」が登場し、関西では屋台文化とともに回転式の焼き器を使うことから「回転焼き」と呼ばれるようになりました。
さらに昭和になると、兵庫県姫路市発祥の老舗「御座候」が百貨店販売を広げ、企業ブランドとして全国に定着します。
実はどれも同じ“円形あんこ菓子”
-
小麦粉の生地にあんこを包み、金型で両面を焼くスタイルは共通。
-
生地の厚みやあんの種類は地域や店によって異なりますが、基本構造は同じ。
-
呼び方・文化・発祥地の違いが現在の多様な名称につながっています。
主な違いと発祥・由来の比較表
| 名称 | 発祥地・発祥時期 | 名前の由来 | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|
| 今川焼き | 江戸(東京・千代田区今川橋付近)/江戸時代中期(18世紀頃) | 販売地「今川橋」から命名 | “今川橋焼き”として屋台で人気に。関東では現在も主流の呼称。 |
| 大判焼き | 明治時代(東京発祥・全国へ拡大) | “大きな判(はん)”=大判から | 今川焼きよりサイズが大きい商品として登場。全国に普及。 |
| 回転焼き | 明治末~大正期(関西圏) | 回転式の焼き器を使用していたことから | 屋台文化とともに広まり、関西では今も定番名称。 |
| 御座候(ござそうろう) | 兵庫県姫路市/昭和29年(1954年)創業 | 企業名「御座候株式会社」に由来 | 焼きたて販売スタイルを確立。百貨店で全国展開。 |
| 蜂楽饅頭(ほうらくまんじゅう) | 熊本県水俣市/昭和28年(1953年)創業 | 生地に蜂蜜を練り込む独自製法から | 九州発祥の人気ブランド。黒あん・白あんの2種類が定番。 |
| 二重焼き | 岡山・広島地方/明治期 | 厚めの生地を二重に焼くことから | 表面が香ばしく、中がふんわり。地方屋台の定番。 |
| あじまん | 山形県天童市/昭和40年代 | 山形の企業名「あじまん」より | 冬季限定販売。東北の冬の風物詩。 |
| 福福饅頭 | 福岡県久留米市/昭和期 | “福を重ねる”縁起の良い名前 | 九州ローカルで販売される縁起菓子。 |
| 天輪焼き(てんりんやき) | 愛知・岐阜地方/昭和期 | 「天に輪を描く形」に由来 | 祭礼や神社縁日で販売される地域銘菓。 |
発祥地をまとめるとこうなる
-
江戸(東京)発祥:今川焼き → 全国の原点。
-
明治期:大判焼き → 今川焼きを大型化し名称を変えて普及。
-
関西:回転焼き → 屋台文化とともに回転式焼き器で進化。
-
兵庫県姫路市:御座候 → 企業ブランドとして全国化。
-
九州(熊本):蜂楽饅頭 → 蜂蜜入り生地の地域ブランドとして確立。
このように、現在の呼び方の多様性は「どの地域で生まれたか」と「いつ普及したか」の歴史に根ざしています。
「大判焼き」や「今川焼き」の全国呼び方一覧!地域ごとの違いマップ
全国では「大判焼き」や「今川焼き」以外にも、地域ごとにさまざまな呼び方があります。
同じ円形のあんこ菓子でも、地方によって名前が変わるのは日本ならではの文化です。
まずは、全国47都道府県での主な呼称を一覧で見てみましょう。
都道府県別・呼び方マップ一覧
| 地域ブロック | 都道府県 | 主な呼び方 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 大判焼き・太鼓焼き・横綱饅頭 |
| 東北 | 青森 | 大判焼き |
| 岩手 | 大判焼き・今川焼き | |
| 宮城 | 大判焼き・あじまん | |
| 秋田 | 大判焼き・どてら焼き | |
| 山形 | あじまん | |
| 福島 | 今川焼き・大判焼き | |
| 関東 | 茨城 | 今川焼き |
| 栃木 | 今川焼き | |
| 群馬 | 今川焼き・大判焼き | |
| 埼玉 | 今川焼き | |
| 千葉 | 今川焼き | |
| 東京 | 今川焼き(発祥地) | |
| 神奈川 | 今川焼き・大判焼き | |
| 中部 | 新潟 | 大判焼き |
| 富山 | 夫婦饅頭 | |
| 石川 | 夫婦饅頭 | |
| 福井 | 大判焼き | |
| 山梨 | 大判焼き | |
| 長野 | おやき(郷土食) | |
| 岐阜 | 天輪焼き・義士焼き | |
| 静岡 | 大判焼き | |
| 愛知 | 天輪焼き・大判焼き | |
| 近畿 | 三重 | 回転焼き |
| 滋賀 | 回転焼き | |
| 京都 | 回転焼き | |
| 大阪 | 回転焼き | |
| 兵庫 | 御座候 | |
| 奈良 | 回転焼き | |
| 和歌山 | 回転焼き | |
| 中国 | 鳥取 | 二重焼き |
| 島根 | 二重焼き | |
| 岡山 | 二重焼き | |
| 広島 | 二重焼き・福福饅頭 | |
| 山口 | 回転焼き | |
| 四国 | 徳島 | 回転焼き |
| 香川 | 回転焼き | |
| 愛媛 | 人工衛星饅頭 | |
| 高知 | 回転焼き | |
| 九州 | 福岡 | 福福饅頭・蜂楽饅頭 |
| 佐賀 | 回転焼き | |
| 長崎 | 回転焼き | |
| 熊本 | 蜂楽饅頭 | |
| 大分 | 回転焼き | |
| 宮崎 | 回転焼き | |
| 鹿児島 | 蜂楽饅頭・回転焼き | |
| 沖縄 | 沖縄 | 大判焼き(屋台・イベント) |
御座候・蜂楽饅頭など、地域ブランドとしての違い
全国で親しまれている円形のあんこ菓子の中には、企業名や地域の特産から名づけられた“ブランド化”したものもあります。
ここでは代表的な「御座候」「蜂楽饅頭」を中心に、地域で独自に発展した呼び方や特徴を紹介します。
御座候(兵庫県姫路市)
兵庫県姫路市発祥の老舗「御座候株式会社」が展開する焼き菓子。
名前は「おそれながら申し上げます(御座候)」という丁寧な言葉に由来します。
黒あん・白あんの2種類が定番で、焼きたてをその場で販売するスタイルが特徴です。
百貨店や駅構内などでも見かける全国的ブランドです。
蜂楽饅頭(熊本県水俣市)
熊本県水俣市で昭和28年に創業した「蜂楽饅頭」は、九州を代表する円形あんこ菓子。
生地に蜂蜜を練り込む独自製法で、ふんわり香ばしい味わいが人気です。
九州では「回転焼き」よりも「蜂楽饅頭」と呼ぶ人が多く、黒あん・白あんの2種が定番。
地元では長く愛される老舗ブランドとして知られています。
その他のご当地ブランド
-
二重焼き(岡山・広島):厚みがあり、外はカリッと中はモチモチ。屋台で人気。
-
あじまん(山形):冬季限定で販売される東北の風物詩。企業名がそのまま定着。
-
福福饅頭(福岡):福が重なる縁起の良い名前が特徴。祝い事でも人気。
-
天輪焼き(岐阜・愛知):「天に輪を描く形」に由来し、神社祭礼でも見かける地域銘菓。
これらのご当地ブランドはいずれも「大判焼き」「今川焼き」と同じルーツを持ちながら、地域の歴史や文化を背景に独自の味と名前が定着した存在です。
今川焼き名前の由来と歴史を解説!
同じ形でも呼び方が違うのは、誕生した時代や地域の背景に理由があります。
ここでは、それぞれの名称がどのように生まれ、どんな意味が込められているのかを紹介します。
今川焼きの由来
今川焼きは江戸時代中期、東京・今川橋付近の屋台で売られていたことが始まりです。
販売場所の名前「今川橋」がそのまま商品名になり、「今川焼き」と呼ばれるようになりました。
江戸庶民に親しまれ、これが全国に広まった“円形あんこ菓子”の原点とされています。
大判焼きの由来
明治時代、今川焼きより大きなサイズで販売されたものを「大判焼き」と呼ぶようになりました。
「判(はん)」は印判やお札の意味があり、“大きく立派なもの”という語感から「大判」に。
そのわかりやすさから全国に広まり、現在では最も一般的な呼称になっています。
回転焼きの由来
「回転焼き」は、回転式の焼き器を使っていた屋台が由来です。
明治末期〜大正時代に関西で流行し、鉄板を回転させて焼く様子からこの名が生まれました。
屋台文化とともに全国へ広がり、特に関西地方では今も「回転焼き」が主流の呼び方です。
御座候の由来
「御座候(ござそうろう)」は、兵庫県姫路市の老舗企業「御座候株式会社」が昭和29年に創業した際につけられた名前です。
「おそれながら申し上げます(御座候)」という丁寧な言葉に由来しており、
“謙虚さと誠実さ”を込めた企業理念がそのまま商品名になりました。
蜂楽饅頭の由来
熊本県水俣市発祥の「蜂楽饅頭(ほうらくまんじゅう)」は、蜂蜜を使った生地が特徴です。
その蜂蜜(蜂)と「楽しい・幸福」を意味する「楽」を組み合わせて命名されました。
“蜂のように自然で甘い味を届けたい”という創業者の想いが込められた名前です。
こうして見ると、「今川焼き」から派生したさまざまな呼び名は、
時代の流れと地域文化の中で育まれた日本独自の言葉の多様性といえます。
まとめ|呼び方は違っても、みんな同じ「円形あんこ菓子」
全国でさまざまな呼び方がある「大判焼き」「今川焼き」「回転焼き」「御座候」ですが、実はどれも同じ製法で作られる円形のあんこ菓子です。
地域や時代の違いが名前に反映されただけで、材料も形もほとんど変わりません。
御座候や蜂楽饅頭、あじまんなどは、それぞれの地域で生まれたブランド名。
長年にわたって地元で愛され、今ではその呼び名が文化として定着しています。
こうした多様な呼び方の違いは、日本らしい食文化の豊かさを感じさせますね。
要点まとめ
-
大判焼き・今川焼き・回転焼きは、基本的に同じお菓子。
-
御座候・蜂楽饅頭・あじまんなどは、地域発祥のブランド名。
-
呼び方の違いは、地域文化や時代背景が生んだ日本独特の風習。
そのほかの豆知識
-
海外では「Imagawayaki」として人気があり、屋台スイーツとして紹介されることも。
-
SNSでは「あなたの地域ではなんて呼ぶ?」が定期的に話題に。
-
呼び方を知ることで、地域の歴史や文化の違いにも気づくことができます。